春から夏へ
今日からぐんと蒸し暑くなり、畑作業も汗のかく季節になってきた。
新しいメンバーも加わりながら、お邪魔した一枚の畑。
暑くなり、虫の出る季節になってきたので、ミントとオイルで作られた虫よけを噴霧して備える。
前回間引いた苗や、直播した小松菜はどうなっているだろうか。今回の畑の緑はどんなもんだろうかと予想する。
今日の畑は、一段と青々としていた。ようやく暑くなってきたという感じだろうか。
畑に立つ
今年の苗はあまり出来が良くないと伺っていた。土の配合(畑の土・腐葉土・くん炭)の調整と、虫害の影響だそうだ。自分の畑の土の特性をよく理解しておかないと、苗ひとつ育てるのも難しい。
購入していただいたトマトとナスの苗は、徒長していた。これは養分をたくさん投入しているからだという。早く育つことが必ずしも良いというわけではなさそうだ。本葉が3枚程度出ているころを見計らって、定植する。一番花をきちんと咲かせることは、その後の苗の良し悪しを決めるらしい。
先月直播きした小松菜ゾーンには、あれ?何もない。と思っていると、ほとんどを虫に食べられてしまったらしい。美味しいものには目がないのは虫も同じなのか。
今日は、ナスとトマトの苗(購入)の定植、以前仕込んでおいたサラダミックスの苗の定植、オクラ・ナス・大豆(枝豆)の播種をした。オクラの種は、2~3年前に仲間が自家採種したものだ。種が巡ってきている。
新しい発見は、定植する際に土を深く掘りすぎないことだ。定植部分がくぼんでいるとそこに水が溜まり、根が腐ってしまう。なので土の高さと同じか苗が少し出るくらいで良い。
ナスとトマトの苗は大きくなることを想定して、支柱を立てる。根を傷つけないように斜めに棒を刺したら、接点の部分を麻紐で結ぶ。この結ぶ作業にみなで苦戦した。まだまだ農民への道は長い。
畑のバランス
今回難しかったのは、畝をどのようにして使うか考えること。日当たり・時期・相性など、総合的に見て複数種をどこに配置するのか決めなくてはいけない。また、播種したからと言って上手くすべてが育つわけでもない。考えれば考えるほど分からなくなってしまうので、仲間と話し合いながらも、お得意の、まぁなんとかなるか!という気持ちで、播種していった。
由井さん曰く、ここでの「農」は農をすればするほど土が良くなるという。同じ畝で同じ作物を作っても、連作障害にはなったことはない。畑を覆っているこの緑は、ただの緑ではないことが分かる。何よりも、仲間はみなこの畑のことを「自然」と認識しているのだ。それが面白い。おそらく土がむき出しの畑に立っても「自然の中にいる感覚」ではないのではないか。ここは虫にとっても作物にとっても人間にとっても「自然」状態である。
撮影係
今日の私は、専ら記録の動画撮影に徹していた。同時多発的に起きている場面を、ひとつに対象を絞って撮影をすることは今までにない難しさ。自分が撮影した動画を振り返ってみると、自分の視点が客観的に見えて新しい発見があった。私は、「全体をみる癖」があることが分かった。例えば「播種」という場面においても、その行為に集中して記録するよりも、その時周囲の様子はどうなのか、土と人間の位置関係は?と意識が散漫としてしまう。すべてを観察対象にしているからこそ、映像にしてみると、漫然としたメリハリのない絵が撮れる。ただ、視覚とは別に映像には音声が入る。周りの声や風の音で周辺の様子をあらわせることも理解したので、映像と音声のコンビネーションを大切にして撮っていきたい。
作ることから食べること
お昼ご飯についても、欠かさず記録したい。それは、農が食に向かう大切な流れであると思うからだ。畑で今が旬のそらまめ(蚕豆と書くらしい。知らなかった。)と、ここの梅でつくった梅干しを炊き合わせたご飯。先月食べたエンドウの「豆」の部分が大きくなった「グリンピース」が使われた鶏肉と豆腐の炒め物。この「作る」→「食べる」の流れが、どうしてここだとこんなにも鮮やかに見えるのだろうか。これを、自分の手で行えるようになったら、同じように鮮やかに感じられるのだろうか。チャレンジしてみよう。
みんながこの時間を楽しみにしながら来るように、私もまた安心できる時間になっていると実感した。
(松田理沙)

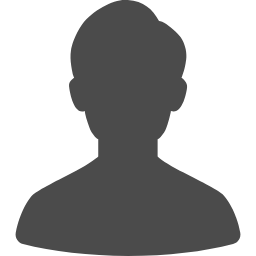

 “建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある
“建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある 3
3 ものがたりをめぐる物語
ものがたりをめぐる物語
川崎市宮前区
2025/05/22
そらまめの写真、いいね。ふわふわのベット感がよく映し出されている。
苗については、がっかりさせてしまいましたね。
人の気持ちもさることながら、野菜の気持ちはさっぱりわかりません。
何かうまくいかないことが起きるとどう対処していいのか、まだわからないことが多いです。
それでも一枚の畑にみなさんが来てくれることは、続けていくことの励みになります。