「侵入者め」。
日本建国のヒーロー、ヤマトタケルに向けての一言である。
いつも思慮深く、誰に対しても丁寧に誠実に接する著者の小倉さんが本文中に遠慮がちに放ったこの言葉が実は、全ての作品の原動力なのではないかと思う。
幼い魂のよりべだった豊かな雑木林がブルドーザーに無残にえぐり取られていくのを泣き叫んで止めようとした少女。己れの無力さ非力さに絶望していた少女が、成長し、今一度足もとを見つめ、蓄えた知性とあの雑木林に育まれた感性で、故郷で今、失われんとしている宝を掘りおこしていく。それが著者の第1作「オオカミの護符」であったならば、この「諏訪式。」は縁あって結びついた土地の人々とその歴史をたどり、また丹念にそれを繋いでいくことで、日本の地理的、文化的、宗教的へそであるとも言える「ただならぬ場所」諏訪から日本社会の構造、歪みをじわりとあぶり出した、著者の「軸足」を保ちつつ、歩みを広げた作品であるといえる。
とは言っても、作品の中央にあるのは決して攻撃的、批判的な眼差しではない。諏訪で生まれ、日本の文化、経済を育んだ人々、そしてその大いなる源である諏訪という土地に対する畏敬と温かい慈愛に満ちた眼差しである。それゆえにこの作品の読後は日本人としてのアイデンティティー(欧米的近代化以前の日本人という意味において)を改めて誇りに思い、コンクリートとアスファルトの下に埋没してしまった、けれども決して消滅したわけではない縄文や古代からの大地の鼓動とその大らかさ、温かさを感じるものとなっている。ちょうど本文中で「それでも、古道は死んだのではない。瞬間的に消えてしまう道は、次々と新しい生命のなかに受け継がれていて、必要なときには、何百キロでも、えんえんと蘇ってくるのである。」という藤森栄一の言葉を引用しているように、丹念な取材の中にそういう桁違いの力強さと大らかさ、母性のような慈しみを感じるのである。それはひとえに著者小倉さんのお人柄によるものとも言えるし、縄文、古代文化から栄えた歴史と、糸魚川・静岡構造線と中央構造線という日本列島の縦横を貫く二大構造線とのまさに交わるダイナミックな場所、諏訪という地のエネルギーを宿しているからとも言えるかもしれない。
個人的には、いつものことながら全編を通して共感するところが多く、母校の先輩であり、娘二人の出身校の創設者である賀川豊彦から始まって、諏訪と同じく養蚕の盛んだった故郷、福島県伊達市梁川町(江戸末期に蚕当計を開発した中村善右衛出生の地)を思い出しながら第一章を読み進め、江戸の身体、明治の精神を持つという諏訪地方出身の「ゴタ」達の錚々たる顔ぶれに感嘆しながら第二章を読み終えた。親しみある寒天の話に昨年訪れた同県伊那のかんてんぱぱガーデン内の寒天商品の多様さを思い出し、また目眩すら覚えるような、魅力的で深遠な諏訪大社の神話から、改めて神話と事実、史実は必ずしもかけ離れていない、むしろ記録としての物語だという意を強くし、またも作中の「私は、これはどうも古代人の観察がかなり鋭く、科学的真相を感知していたことを示す一例だと思うのです」という藤森栄一の言葉に深く同感した。ちなみに第三章に出てくる古材から新たに今風のおしゃれな建物を建設している「ReBuilding Center (略してリビセン)」とも遠いながらご縁がある。また、教育に携わる者の端っくれとして、三澤勝衛の話は胸に迫るものがあった。藤森栄一、新田次郎等、見事な教え子達を輩出した、自らも研究者であり熱心な教師である三澤。真の教育者たるものはこうでなければならない。自分の不甲斐なさが悲しくなるが、激務に枯れそうになる熱意に火をつけてもらった。
以上、小倉さんの丁寧で着実な取材に基づく文章に対して、なんとも不勉強で乱暴な文章となり大変失礼とは思いつつ、読後の感想を述べさせていただいた。まだまだ読み込む必要があることは重々承知している。そしてまた何度も読み返し、新たに感動を頂ける魅力的で重厚な作品を再び生み出して頂いたことに大変感謝している。
諏訪湖を空とし、ゆるやかに、けれども力強く輪になり広がる人と人、文化、経済の結びつき。かつての「講」が「日本列島の細胞のようなものだった」ように、この「諏訪式。」で解き明かされ広がった結びつきが縦に横に層となり、この諏訪の土地のエネルギーとともに曼陀羅のように日本へ、さらには世界へと広がるよう。
風土を宿した身体に憧れを抱きつつもひしめく情報に閉じこもりがちな身体と気持ちを、今一度見つめ直し、新たに結い直す、そんな大きなきっかけを頂いた本となった。
*写真は諏訪SAから 2020年12月30日 飯島本人撮影

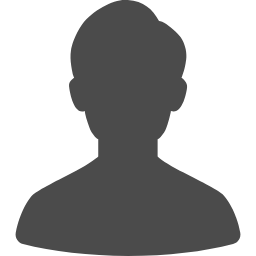




 “建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある
“建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある 3
3 ものがたりをめぐる物語
ものがたりをめぐる物語
横浜市戸塚区
2021/01/10
小倉様
ご返信ありがとうございます。いつも無作法にも感情のまま投げかける思いを、数倍にも数十倍にも深めてくださり感謝です。また広く深く、丁寧に事象を考察する学びの機会を与えて下さりありがとうございます。「諏訪式。」によって膨らむ世界に心が躍っています。再読、再々読をしながらさらに諏訪という土地の魅力に、また「諏訪式。」から見えて来るこの国の姿に近づいていきたいと思っています。