諏訪のたね プロジェクト 第1話
“建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある
2025年7月19日(土)に、伊東豊雄さんと藤森照信さんをお迎えしてトークセッションを開催しました。その様子を前編(鼎談)、後編(質疑応答)と二つに分けてまとめました。まずはこのページで前編の鼎談をお届けします。聞き手は、小倉美惠子(文筆家)です。
かねてより、信州の諏訪にルーツを持つお二人の建築家を諏訪に(開催地は茅野市)お招きしたいと思っておりました。それはトークセッションの表題にも表れている通り、お二人の建物は故郷である諏訪からどのような影響を受けているのか、あるいは受けていないのかも含めて、言わば「作風と地域性」との関係を浮き彫りにしてみたいと思っていたからです。
お二人の初期の頃の建物が諏訪湖を挟んで対面しています。下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館(伊東豊雄 設計)と神長官守矢史料館(藤森照信 設計)。実際に諏訪を訪れ、その建物をご覧になった方ならばお分かりいただけると思いますが、一見して、お二人の作風は全く異なります。
それについては今回の鼎談の中で、山の姿になぞらえながら次のように述べています。
「互いに別々の麓から同じ頂上を目指してきたように思う」と。
別の麓からということについては、お二人の建物を見比べれば容易に想像できますが、同じ頂上とはどういうところなのか。きっと、この映像を見ていただければ、想像してもらえるのではないかと思います。
とはいえ、これは私の個人的な見方に過ぎないと思いますが、「同じ頂上を目指してきたけれども、同じ頂上には立っていない(立てない)」というような微妙な距離感をお二人の表情から感じました。言葉と表情(気持ち)が一致していないところが、僅かながらに見受けられたのです。この辺りを感じ取れるのが、映像を観ることの面白さです。さて、その点について皆さんは、どのようにお感じになるのでしょうか。
互いの作風を認め合いながらも、建物を通して実現したい世界観は容易に他者と交差するものではなく、むしろ自分が成すべき道と捉え、それぞれがそこに直向きに歩んでいく覚悟のようなものを感じました。(由井)
伊東豊雄 <ゲストスピーカー>
1941年生まれ。父の郷里の長野県下諏訪町で育つ。中学校3年生の途中で上京。東京大学工学部建築学科卒業。主な作品に、「下諏訪町立諏訪湖博物館」、「せんだいメディアテーク」、「まつもと市民芸術館」、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」、「台中国家歌劇院」(台湾)、「EXPOホール」など。日本建築学会賞、ヴェネチア・ビエンナーレ金獅子賞、プリツカー建築賞など受賞。
藤森照信 <ゲストスピーカー>
1946年長野県茅野市生まれ。建築史家 建築家 東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授 工学院大学特任教授
『日本の近代建築 上・下』(岩波書店)『建築探偵の冒険 東京篇』(筑摩書房)『茶室学講義―日本の極小空間の謎』(角川文庫)『藤森照信作品集』(TOTO出版)など著書多数。建築作品として〈神長官守矢史料館〉〈近江八幡ラ・コリーナ草屋根〉〈多治見市モザイクタイルミュージアム〉など。近年は国内外にフリースタイルの茶室を制作している。
小倉 美惠子 <聞き手>
1963年 神奈川県川崎市宮前区土橋生まれ。 文筆家・ささらプロダクション代表、諏訪円卓会議コアメンバー。アジア21世紀奨学財団、ヒューマンルネッサンス研究所勤務を経て、2006(平成18)年に(株)ささらプロダクションを設立。2008年映画『オオカミの護符』で文化庁映画賞文化記録映画優秀賞他受賞。2011年「オオカミの護符」を新潮社より上梓。2017年川崎市文化賞受賞。2022年「諏訪式。」を亜紀書房より上梓。
🍀 🍀 🍀 諏訪のたね スカラシップ(奨学制度)🍀 🍀 🍀
私たちは諏訪で学ぶ学生を応援しています。
伊東豊雄
岩佐とし子
田中輝明
細川強
匿名支援者2名


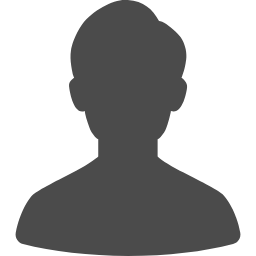


 “建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある
“建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある 3
3 ものがたりをめぐる物語
ものがたりをめぐる物語