昔に戻りたいわけではない
さりとて このまま進みたくはない
気持ちの晴れぬまま
ものがたりをめぐる旅に出かけることにする
ものがたりをめぐる物語 前編 地下の国へ より
映画は、臨床心理学者の河合隼雄や神話学者のジョゼフ・キャンベルの「物語論」に触発され、製作を開始した。作品の舞台は信州の諏訪。諏訪大社の縁起物語とされる「甲賀三郎」伝説を深く読み解いていく。
主人公の甲賀三郎は、突然、姿を消した姫を探しに蓼科山(八ヶ岳)の人穴から「地下の国」をめぐることになる。三郎は様々な国々を訪ね歩いた末に、不思議な女と出会い、結ばれる。やがて子も生まれ、三郎は地下の国で幸せな日々を過ごすようになる。ある日三郎は、地上の国のことを思い出し、妻や子にその気持ちを打ち明け、地上へ戻る旅に出かける。様々な困難を克服して三郎は再び地上に戻るが、池の水面に映る自分の姿を見て、愕然とする。蛇に姿を変えていたからだ。
この物語は、今を生きる私たちに何を語りかけようとしているのか。諏訪という地域とどのような関わりのある物語なのだろうか。穴、地下、蛇という言葉が奇妙に心に響き、記憶に残る。
映画は、今から10年以上前に製作が開始され、その直後に東日本大震災が起きた。本来、諏訪で完結するはずだった映画は、突然、諏訪を離れ、陸前高田市に至り、まるで地下をめぐる三郎のように彷徨っていくことになった。
2022年2月、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が未だ収束しない中、映画は「再び地上に戻り」完成する。映画はこれまでの日本の歩みを振り返りながら、これからの私たちの生き方を問いかけていく。
あなたは、この映画の「地下に潜む」メッセージをどのように受け留めてくれるのだろうか。ものがたりをめぐる旅は後編に続く…
映画作家 由井 英
監督・編集:由井 英
制作総指揮:小泉修吉、小倉美惠子 撮影:秋葉清功、伊藤碩男、筒井勝彦
録音:高木創 語り:清水理沙 描画:近藤圭恵 ピアノ演奏:大森晶子 音響効果:高津輝幸、高木創
レコーディングスタジオ:TAGO STUDIO MAスタジオ:AQUARIUM、Studio GONG
出演:河野和子、塩川悠太、荻原節子、オギュスタン ベルク、山中康裕
助成支援:公益財団法人トヨタ財団
協賛支援:ホテル尖石、ライフプラザ マリオ
協賛支援:柴原みどり、宮越博子、速渡普土、飯島聡子、もりしたかずこ、小倉弘之、小倉麻由子、島正孝、中村真知子、野本紀子、堀内幸春、佐藤由紀子、高見俊樹、本木勝利、牛山一貴、飯田千代、飯田なつよ
撮影協力:北沢一行、熊澤祥吉、昔ばなし語りの会あかり、佐久市佐久城山小学校、東京ステーションホテル、正福寺、本御射山神社、八劔神社、諏訪市博物館、井戸尻考古館、茅野市尖石縄文考古館、上桑原牧野組合、ヒュッテ御射山、公益財団法人八十二文化財団、おかん塚古墳
写真提供:紺野利男、渡辺雅史、小倉美惠子。友澤悠季、小林信雄、平尾隆信、阿部史恵、中野貴徳 タクミ印刷有限会社、市川一雄、八劔神社、諏訪市博物館、八ヶ岳美術館
画像提供:山梨県立博物館、国立国会図書館 映像提供:神奈川県川崎市
物語出典:「甲賀三郎」 限定復刻版佐久口碑伝説集南佐久篇 |語り:岡部いちの採録より改編
▶︎ シネマセッションのご案内
ささらプロダクションでは新たな映画を観る場「シネマセッション」を企画してくださる方々を募集しております。旅館やホテル、美術館や博物館、中小企業から大企業、そして様々な業態のお店のオーナー、ぜひあなたの大切な場でシネマセッションを開催してみませんか。詳しくは弊社Websiteの「シネマセッション」をご覧ください。ご不明な点などございましたらお気軽のお問い合わせください。
・これまでの主な団体映画会(シネマセッションを含む)
2025.04.29 明治大学政治経済学部 藤本ゼミ
2025.02.08 土曜日の会スペシャルイベント 川崎市宮前市民館 前後編上映
2024.02.17 公益財団法人八十二文化財団 主催映画会 前後編上映
2023.04.28-05.11 映画館シネマネコ 劇場初公開・前後編上映
2023.03.25 佐久市生涯学習センター(野沢会館)・前後編上映
2023.03.04 下諏訪町総合文化センター・前後編上映【主催:下諏訪町・下諏訪町教育委員会】
2022.12.04 陸前高田コミュニティホール・前後編上映【主催:陸前高田映画会実行委委員会】
2022.08.27 諏訪市文化センター 前後編 初公開【主催:諏訪市博物館・大昔調査会】
2022.06.04 伊佐ホームズ ギャラリー櫟
2022.05.28 東京都埋蔵文化財センター 前編 初公開
青梅シネマネコ劇場公開アンケートより
知人が「素敵な映画があるよ」と教えてくれました。「ものがたりをめぐる物語」を見て、不思議な映画だと思いました。「風土」を地下の国へ、地上へと、、つないでいるものは何か?考えます。神様の世界、人間の世界、間(あわい)の世界。風土に生きることを大切に感謝すること。古代、現代、未来へとつむいでいくものがたりのように郷土、風土の文化、歴史に向かい合いたいと思いました。
(青梅市在住 女性)
感動的な映画でした。上映後のトークの際に、由井氏自身も会場のお客様も石川氏も触れられていませんでしたが、私個人としては、ドキュメンタリーフィルム(川崎のニュースや白黒の写真の数々)などにいたく心が痛み、現在の日本全体がこうして壊されてしまった現実を日本人全てが知るべきだと思いました。多くの人々に見てほしい、考えてほしい作品です。前後編2時間ぶっ通しでも問題ないと思いました。石川さんの無事な姿を確認できて安心しました。(2023.4.29 上映後、写真家石川直樹氏と対談)
(60代女性 東京都練馬区)
▶︎ 皆さんの感想を下記のコメント欄よりお寄せください。
次回以降の作品に活かして参ります。
お時間を頂くことになりますが、できるだけご返信致します。


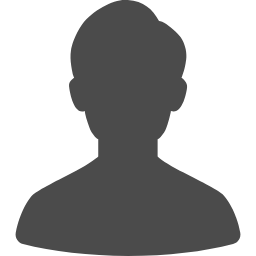




 “建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある
“建てもの” の 向こう側には 諏訪 がある 3
3 ものがたりをめぐる物語
ものがたりをめぐる物語
川崎市宮前区
2022/03/20
コメントをお寄せ頂きありがとうございます。「作品に新たな光が差し込んできた」という気持ちです。作家冥利に尽きます。
私たちはいつの間にか、自分達の進む先に未来があり、問題の解答を外に求めるようになった。かつて未来は過去との関係性の中にあり、そもそも解答は外ではなく自分の内にあると考えてきた。もしそうであるならば、一体いつから変わってしまったのだろうと考えてみたくなる。
外から見る限り、マイケルジャクソンのムーンウォークは美しい。奇跡的と言っていいほど。しかしムーンウォークは、他の誰でもない私たちの姿の焼き写しなのだ。
進んでいると思っても、後退している。大地にしっかり足を下ろしていると思っても、そこは月の上のようだ。さまざまな関係性が巧みに何者かによって変えられている。すり替えられている。きっと今この瞬間も。それをこれまでのように何者かに問題を押し付け、机の引き出しの中にしまえば済むのだろうか。後で引き出しを開けるつもりはあるのだろうか。何者かは一体誰なのか。
必死に前に進もうをしている私たちは健気であるが、果たしていつまでその必死さを保つことができるのか。前に進むことを諦められるのか。関係性を壊してでも、強引に力尽くで進もうとするのか。
井村さんのコメントを読みながらそんなことを考えました。後編もぜひご覧ください。